ブタペスト紀行 -(1)動乱後のブタペストへ-
- 事務局
- 2017年11月23日
- 読了時間: 7分
更新日:2020年10月9日
1.動乱後のブタペストへ
ローマオリンピック日本水泳選手団 山本健
1956年10月、水球競技では世界最強であり常勝軍団であるハンガリーナショナルチームがメルボルンオリンピック参加のためバスで隣国オーストリアに向かっていた。
大半の選手が眠りについているとき、反対車線を轟々たる地響きと共にすれ違う騒音により覚醒した。それは完全武装した数百台の戦車隊であり、闇に浮かぶ国籍マークはソ連の碇印であった。やはり又来たかという思いにチーム全員が押しつぶされるような暗澹とした思いを強いられた
この前日、自由化を求めるハンガリ―政府を圧力で翻意させんとしてブタペストに進行してきていたソ連軍戦車隊は住民の抵抗と、時のハンガリー政府との話し合いの結果市内から国境へ撤退したばかりだったのである。数日前からソ連国軍は自由化を求めて立ち上がった学生を中心とする愛国者たちを封じ込めるため、本国から2000両の戦車隊を派遣しブタペスト市内各所に駐留せしめ、ソ連衛星国としての義務と立場を認識し忠誠を誓うよう同国に対し高圧的に要求していたのである。そして折衝の末、それらが叶わないとして市民の歓声の中を悄然として国外へ去ったはずだったのである。
ハンガリー水球の代表選手たちはブタペスト市内で抵抗運動をすることよりも、自由世界への健全な訴えをオリンピックという舞台で示すことを選び、戦車撤退を見据えて故郷を後にしてきた矢先であり、ここで見せられた、いつもながらの欺瞞に満ちたソ連のやり口に暗然とした思いを抱いたのである。
翌朝を期してブタペスト市内に突入した戦車隊は、今度は問答無用の行動に出た.市内中心部は厚い石材やレンガにより数百年前から4~5階建てに建築されさらに数棟にわたる建物群は時には100メートル以上、交差点から次の曲がり角まで連なり、あたかも城壁のような堅牢感のある建造物であった。
その建物からの小銃や手製の火炎瓶による抵抗に対し、ソ連軍は長大な戦車砲を駆使して石壁に無数の弾痕をしるし、時にはビルを破壊、さらには住民義勇軍の手製バリケードを乗り越え、殺戮していったのである。そして、学生を中心とした自由を求める抵抗軍は車の屋根に不当な砲撃で命を失った傷だらけの仲間の遺体を積み、各階の住民に蜂起参加を呼びかけ、市中を巡つた。
そして抵抗をためらう自国警察から武器を譲り受け、少数の退役軍人の指導の下、学校キャンパスをもって陣地を築きソ連軍に対峙したのである。しかしソ連正規軍に対する市民抵抗は当然の帰結として市民数千人の殺戮の末、数日で終ることとなつた。
そして、この後20万人にも及ぶ民族亡命、国外脱出を経て、36年にわたるソ連共産政権の圧政が続くのである。
一方この時同時に開催されていたメルボルンオリンピックに参加したハンガリーチームは、この理不尽な暴挙に対する怒りと同国民への圧倒的な同情を持つ世界的な与論、それを顕著に表す国民、観衆に熱狂的に歓迎された。
そして水球競技では互いに優勝候補であるハンガリーとソ連が事実上の決勝戦と言われる準決勝に臨んだ。水球はプレー中水中では事実上かなり乱暴なこと(手足をつかんだり、水着を引っ張る、など)が許され,反則行為ではあるが、レフェリーの目を盗んで、あいてに体力的な圧力をかける。
足がたたないので格闘中相手を水中に沈めることも頻繁である。この様な状況で試合が進行中、ついに世界に喧伝される歴史的な傷害プレーが起こったのである。それは「血染めのプールとして長く語り継がれた事件で、ソ連のフォワード選手がエビアン、ツアドールというハンガリー選手を殴打し目じりを切った多くの血が流れ、試合が中断続行不可能になったものである。
プールサイドで血を流す選手の写真が、おりしもブタペストでの殺戮をほうふつさせるもので,同情と怒りをもって全世界に報道された。この後ハンガリー選手は数年間故郷に帰ることが危険と言われ、全員がアメリカに亡命したと言われている。
4年後1960年イタリアローマでのオリンピックに自分を含め日本水球選手団が参加した。
大会後当時は初めてとなる、鉄のカーテンの向こう側に入国し、親善試合を行うということで、ユーゴスラビア、ハンガリーに遠征した。ローマ大会では3位であったハンガリー選手に動乱亡命後の事を聞くと全員無事帰国し、家族とも事なきであったとのことで安心した。
しかし事件の当人であるソ連の怪物選手は依然として主将に納まり周囲を睥睨していたのは気味悪く近寄りがたいものであった。
ブタペスト市内に入るとまだ動乱後4年目ということで、町は暗いビルが並び、街路灯も少なく、重苦しい雰囲気に包まれていた。車が少なく閑散とした大通り、中央に市電が走り、朝夕は通勤と思しき人で埋まっていた。そのほかに人の集まる場所は共同市場だけで、後は荒涼とした広場を地味な洋服の市民がうつむいて歩いていた。
特に石やコンクリートのビルが明瞭な無数の弾痕を刻まれたままで、我々の泊まったホテルの部屋の窓から手を出して手のひら大の弾痕穴をなぞって、当時の様を実感したが、それを口にするのも憚れる雰囲気であった。
いまだ共産圧制政治のもとで隠しようのない痕跡や暗い印象は常について回り、我々選手団の世話係のようにして常に一緒にいたハンガリ―側の関係者が帰国直前に、いきなり流暢な日本語を話し始めたのには驚いた。思うに何か国益に沿わない人間が紛れ込んでいないかを会話等を盗み聞きして判断していたのではないかと疑わざるを得なかった。
そういえば不自然に近くに立っていたり、時折鋭い目つきをしていたことを思い出す。いったい彼は何処の国の人だったのだろう。少なくとも圧政下の善良なハンガリアンではなかったと思う。
選手団はバスでプールへの行き帰りの他自由に外出することはなかった。危険は感じなかったが、何が起こるかわからないのが選手団首脳部の考えだったのだろう。もっとも夜間、ハンガリー選手が内緒でレストランに案内してくれた時でも、何となく互いに片言で話したが、警戒心が先に立ち、あまり深い話はしなかった。
例えば動乱や亡命、家族、生活の話などはあいまいな微笑で返され、相手の背負っている重いものに気を遣う羽目となった。そしてまだ深夜には早い時間にもかかわらず、夜間外出制限を背負っている彼らがそそくさと帰途に就くのを引き留められず、昼間の喧騒がうそのように静まり返った夜の街並みへ急ぐ後姿を見送ったのであった。
試合は王者ハンガリーチームに胸を借りるようなものであったが、一般観客の水球に詳しいことは伝わってきた。それはあたかも日本の野球場での観客反応のようなものであり、試合中、珍しいプレーや技術にいち早く反応が返ってきた。我が高木選手の独特なシュートに対しどよめきが起こったのはさすがであると思った。そして好プレーに対してはわけ隔てのない拍手が起こり水球をかわいがり親しんでいる様子が何度もうかがえた。
市内でも一般の市民の水球選手への人気は高く、歩道の上で求められるサインはちょっと立ち止まると行列になるほどであり、選手名を知っている人もいて驚かされた。
聴けばハンガリー水球で人気のあるキャパテイ選手などはその人気が日本プロ野球の長嶋なみであり、奥さんは有名な映画女優であるそうだ。日本国内でマイナースポーツ界にいる我々選手が顔を見合わせ、その格差を感じあう始末であった。また我々の試合の前に同じプールで少年たちが水球の試合をやっていたが、何か違和感がある。普通水球は水の中のスポーツであるから大声を掛け合って、お互い位置や意志そのものを確認しあう。それが実に静かなゲーム運びで行はれている。よく見ると彼らは言葉の喋れない人たち同士であり、彼らの世界での対抗試合をやっていたのだ。まさに日本での草野球であり、また50年前に今でいうパラリンピックのゲームをやっていたのである。改めてこの国での水球というスポーツの深みを感じさせられた。ここまで競技が国民に浸透することにより、人口が日本の十分の一ぐらいであっても、世界を制する水球チームが育っていると感心するものである。(続く)
※写真はPremier Press Publishingの発行物です。


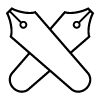
















コメント