歴史研究会 府中市郷土の森博物館 視察例会
- 所沢三田会歴史研究会
- 2025年7月8日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年7月9日
梅雨の合間のどんよりとして蒸す水無月の9時20分、秋津駅に8名が集合し、新秋津から府中本町駅まで武蔵野線にて移動し、南武線に乗り換え分倍売河原駅で下車し、バスにて現地まで移動しました。天気予報は雷と雨の可能性を示唆しました。
「府中」という市名は律令時代に武蔵国の国府が置かれた地であることに由来し、「国府所在地」を意味するそうです。前回の国分寺視察で記した通り、鎌倉時代末期の1333年(元弘3年)、足利尊氏に呼応して討幕軍を起こした新田義貞の20万7千兵まで膨れ上がった軍勢は鎌倉街道沿いに南下し、「小手指原の戦い」に続いて「久米川の戦い」で相次いで幕府軍を撃破しました。幕府軍は多摩川の「分倍河原の戦い」で大敗北を期し鎌倉幕府崩壊へと繋がります。分倍河原という駅の名称はこの戦いが由来です。
府中市郷土の森博物館(下記ご参照)は東京都府中市にあり、1968年(昭和43年)に設立された府中市立郷土館を前身として1987年(昭和62年)、現在地に多くの懐かしい歴史的な建築物を含む森全体が一体となって開館した総合野外博物館です。博物館本館を核に、約14 haにおよぶ広大な園内を持つことに大きな特色があります。その園内は「府中の縮図」を意図してゾーニングされており、府中市の中心部にあるケヤキ並木や甲州街道、府中崖線(ハケ)に見立てた通りや地形を骨格として、府中町役場や甲州街道沿いにあった町屋、茅葺農家、さらに田んぼや畑、雑木林を配置しています。その使命とは、「府中の歴史と文化と人の調和に貢献すること」としており、かつて市内にあった江戸時代から昭和初期の建物8棟を移築・復元しております。さらに、水遊びの池や梅園など、レクリエーションの要素を含んだ空間も備えています。博物館本館は、府中の歴史・文化・自然を学べる常設展示室のほか、最新鋭の投映機を備えたプラネタリウムを併設しています。

入口で入場料300円を支払い園内に入ると、ケヤキ並木に沿って「紫陽花祭り」をやっておりました。しかし最盛期はかなり前のようで、花を保っているのが少なかったです。しかし、日本固有の「額アジサイ」(下記左側)が美しく咲いていました。
ちなみに、普通に咲いている一般的な紫陽花は「西洋アジサイ」(上記右側)で、日本原産の「額アジサイ」を欧州にて品種改良したものが逆輸入されたものです。紫陽花の花言葉は、若干色っぽく「移り気」とか「浮気」です。由来は、紫陽花の花が咲いてから段々と色を変える特性によるものだそうです。
ケヤキ並木を左折すると、旧府中尋常小学校が現れます。1935年(昭和10)に府中市寿町建てられ、その後、府中市立府中第一小学校の校舎として1979年(昭和54年)まで使用されていました。同小学校は北多摩随一の規模を誇った2階建ての木造瓦葺き校舎で、その中央部分である玄関前後をこの公園に移築し復元されました(下記ご参照)。内部の教室には、昔の教科書などが展示され、府中ゆかりの詩人・村野四郎の記念館が併設されています。

村野四郎という詩人を筆者は知らなかったのですが、動揺「ぶんぶんぶん」や「巣立ちの歌」などを作詞している有名人だそうで、記念館では同氏の生涯や作品を紹介しています。但し、紹介パネルに村野四郎は東京商科大学受験に落ち、一浪して再び挑戦して叶わず、慶應義塾大学理財部(現経済学部)に入学したとあり、しょうがないから慶應に来たというニュアンスを感じ、若干カチンときました。

再びケヤキ並木に戻り先に進むと、1921年(大正10年)に建築された典型的な大正ロマン風の息吹を感じさせる旧府中町役場庁舎(下記ご参照)が現れます。玄関側には急勾配の屋根面から垂直に突き出したドーマーウィンドウという窓を持つ洋風下見板張りの2階建てで、裏手には和風の平屋が接続されており、元々府中市宮西町にあったもので、東京都指定有形文化財となっています。

右隣に旧府中郵便取扱所(下記ご参照)があります。郵便制度が開始した翌年の1872年(明治5年)に府中宿で最初に設置された郵便取扱所で、府中番場宿の名主兼問屋である矢島家の江戸時代後期に建築された旧矢島家住宅に併設されました。丸い郵便窓口が当時を思い起こさせます。元々府中市宮西町あったのを移転し復元しました。

ケヤキ並木まで戻ると1888年(明治21年)に建築された旧島田家住宅(下記ご参照)があります。江戸時代から続いた商家で、移築に際しては建築当時の伝統的な工法を再現し、3年をかけて復元されたものです。

旧島田家の対面に明治初期に建築された旧田中家住宅(下記写真左側)があります。幕末から明治期の呉服店で、府中宿の代表的な大店です。明治天皇の「御座所」としても使われた奥座敷を移築し、当時の資料を基に屋敷全体を復元された立派な建物です。いつの間にか雷と雨という天気予報が大きく外れ、青空に晴れ渡り、猛暑が復活し、うだるような暑さに救いの神が現れました。旧田中家の一角で「平次のおうどん 古民家カフェ」というオシャレなうどん屋(下記写真右側)が併設されておりました。若干早めでしたが、11時オープンと同時にうどん屋に飛び込み、冷たいビールでのどを潤し、コシのある美味しいうどんと天ぷらを堪能しました。

ビールでほろ酔い気分の後、暑さを避けるためにクーラーの利いた博物館と併設されるプラネタリウムに移動しました。プラネタリウムの上映まで若干時間があったので、博物館を散策しました。大國魂神社の有名な「くらやみ祭り」の全貌や古代国府の誕生経緯などを学びました。
プラネタリウムの時間が来たので600円を支払って入場しました。先ずは『今夜の星空と “天球の物語”』で始まりました。春の夜は、空の高い所に柄杓の形に並んだ7つの星「北斗七星」が輝いています。北斗七星は、比較的明るい星々からできていることや、日本ではほぼ1年中見られます。その柄杓の先にある2つの星の間隔を、柄杓の先端から5倍に延ばした距離にあるのが目的の北極星だそうです。北極星は常に北にあり船乗りの命綱であり、北斗信仰の中心でもある天空でも最も重要な星です。同じように、北西の空に輝くカシオペヤ座も北極星を探す手助けとなります。

その後は『ショーティと魔法のサンゴ礁』というプラネタリウムの天球をフルに使ったアニメーションが上映されました。カクレクマノミのショーティ、妹のインディゴ、そしてのこぎりサメのジェイクという3匹の魚たちがみんなで平和に暮らせる魔法のサンゴ礁を求めて冒険の旅に出るというストーリーでした。その後、筆者は個人的にミュージアム・ショップで公園内の梅園で製造された珍しい梅ジャムを購入しました。甘酸っぱい梅ジャムはバタートーストにピッタリで美味でした。
そして、そろそろ程よい時間となりましたので、正門を出て、観光物産館を回り、帰宅の途につきました。
以上
文責:伊藤芳康(S51経)
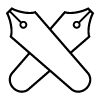























見事な小旅行記ですね。伊藤さんの博学と文章力に感心しました。
有難うございました。
篠塚文雄