天網恢恢、疎にして漏らさず(逆説)
- 事務局
- 2022年7月4日
- 読了時間: 7分
『天網恢恢、疎にして漏らさず』といきなりタイトルに知らない四文字熟語が現れ、読み進むと最後にやっとその意味がわかります。そして、寄稿文は一気に背骨が通るようになります。見事です。栗原慶明さんのファミリーヒストリーです。そのルーツは・・・。是非ご一読下さい。
伊藤芳康(S51経)
天網恢恢、疎にして漏らさず(逆説)
栗原 慶明(S47経)
今年(2022年)の総会会場で杉本会長から再度の投稿要請がありましたので、恥を顧みず駄文を弄することといたしました。
1.四代小史
私は1949年(昭和24年)4月に長崎県佐世保市で生を受け、中学卒業まで現地で育ちましたので、やはり自分の故郷は佐世保ということになります。
偶々ではありますが、中学の担任教諭は作家村上龍の父親村上新一郎氏(画家・故人)であり、我が山澄中学校の野球部を抑え込んだ隣の旭中学校の誇る名投手は後のクールファイブの歌手となる若き前川清でした。
今年2022年(令和4年)は明治155年に相当するようですが、私の曽祖父(父の父の父)栗原種芳(たねよし)は、嘉永4年(1851年)に肥前鍋島藩の支藩であった小城藩藩士の家に生まれました。 因みにこの年は、天保の改革を指導した水野忠邦(肥前唐津藩主)が56歳で没した年でもあります。
畢竟、種芳は17歳の時に明治維新を迎えることになるのですが、薩長土肥の一角として率先して藩籍離脱を推進した鍋島藩の方針により、僅かな退職金を元手にすぐにも自身の才覚で生計を立てていかなければなりませんでした。
明治の世を迎え、日本国が西欧列強に追いつくための「富国強兵」に向けて、一介の寒漁村に過ぎなかった佐世保村が天然の良港として横須賀・呉と並んで海軍鎮守府に指定されたことを機に、種芳は佐世保で企業する途を選んだのです。
1902年(明治35年)に村から市へと発展した市議会において参事を務める傍ら、家具・雑貨商を中心に上海貿易や石炭調達を加えて海軍御用達としての事業を拡大していきました。
1904年(明治37年)から翌年にかけての日露戦争における日本海海戦では、当時世界最強と謳われたバルチック艦隊を完膚なきまでに撃滅した東郷平八郎連合艦隊司令長官ですが、娘と娘婿(海軍)が新婚の一時期、栗原商店を寓居としていたことから度々東郷の来訪があり、今も東郷の墨蹟が残っています。
祖父八郎は1889年(明治22年)に生まれ、長崎高等商業学校(現在の長崎大学経済学部)を卒業後、種芳が創った事業を継承・拡大し、レンガ工場建設の他、佐世保から早岐(現在のハウステンボス近く)までの鉄道建設を計画しました。
今でも鉄道省(当時)へ宛てた墨書きの企業目論見書が残っていますが、その多忙な業務の渦中1925年(大正14年)に急性肺炎のため、当時は抗生物質もなく36歳の若さで急逝しました。

父一郎は1917年(大正6年)に5人兄弟の長男として生まれ、家長である父親の夭逝という家族の命運が暗転した時は僅か8歳であったため、佐賀県鹿島の親戚に預けられた後、以前栗原商店で番頭を務めていた人が興した佐世保の商店で長らく丁稚奉公の日々を送りました。
しかし長ずるに及んで大学進学への夢を捨てきれず、向学心に燃えて慶應義塾大学を受験し入学しました(昭和16年理財卒)。
入試科目に「そろばん」が残っていた最後の年だったとは生前よく言っていたことです。
その後太平洋戦争の激化に伴い、塾での親しい友人たちが次々と戦死していく中、小柄だった父は大倉グループの軍需工場で経理を担当していましたが、日本が既に制空権を失っていた昭和20年7月、現在の福生市に架かる多摩川の鉄橋で電車の乗客が米機(グラマン)の掃射を受け、多くの死亡者が出た中で、父は左足に被弾し重症を負ったものの九死に一生を得ました。
僅か3か月前に母と結婚したばかりの受傷に対し、心配した母の父(私の祖父)の薦めで当代一流の九州大学医学部病棟に移り、終戦後も左脚を何とか残すために外科手術を何回も繰り返さなければなりませんでした。
2.父の厳命
1965年(昭和40年)春、私は幸いにして慶應義塾高校と慶應志木高校ならびに長崎県立佐世保北高校の3校に合格することができました。
当時、塾高(日吉)は慶應付属校の本校であり志木高校は農業高校というイメージがあったため、当然のように塾高入学書類を準備していましたが、提出の前日になって九州の父から電話があり「志木に行きなさい」との厳命を受けました。下宿することが決まっていた叔父(父の次弟)の家が石神井に在り、日吉までの通学経路には新宿・渋谷という田舎者にとっては刺激の強すぎる繁華街があったことも一因だったのではないかと思っています。
尤も志木高は私が入学した年から「農業実習の時間」が無くなり、普通高校に転換したのですが、後になってみると勝手なもので「農業実習も経験したかった」との思いも残りました。
3.松永安左エ門との出会い
志木高入学式の朝、当時まだ板張りの電車であった東武東上線で志木駅を降り、歩いて向かった正門の先に胸像が見えたので福沢諭吉だとばかり思って近づいてみたら、実は松永安左エ門を顕彰したものであることが判り、これが最初の翁との出会いでした。
更には志木高の広大な土地(当時約6万坪)が翁の慶應義塾への寄付によるものであることはその頃から聴いてはいましたが、翁についてはそれ以上のことを知らないままに、その後は迂闊にも過ごしてきたのです。
再度の出会いが訪れたのは、家内の実家があった所沢に長年住んでいたのですが、41年の会社勤めを終えて退職後、生涯学習センターで「柳瀬山荘と松永安左エ門について」柳瀬荘管理人・針生清美氏による講演会に偶々参加した時のことです。
その会場には中原さんはじめ所沢三田会の方々が何人か出席されていたと思いますが、松尾さんに「柳瀬山荘の敷地を整備するボランティア作業に勿論栗原さんも参加しますよね」と云われ、当初は何のことかと当惑しながらもその後参加させていただくことにしました。
そこでは稲村さんはじめ三田会から諸先輩が参加されており、農業サークルの方々と共に月一回の整備作業を楽しむうちに耳庵(茶人・松永の号)の想いや人との繋がり・事績に感じ入るようになりました。
余談ですが、父は私が高3の秋に受傷の影響もあり50歳の若さで亡くなりましたが、その年の夏休みに帰省した折、突然「茶道の精神」について語ってくれたことがあり、翌春に大学(日吉)進学の際は、何の躊躇いもなく「茶道会(慶應では茶道部でなく)」に入り、貴重な経験(青山根津美術館茶室での月例会、三井本家の管理する京都・真如堂での夏合宿、裏千家・表千家・武者小路千家訪問など)と素晴らしい人々との交流に恵まれました。
柳瀬荘では、悩みを抱えて耳庵の元を訪ねたと思われる近衛文麿が茶室に「斜月亭」と命名した話を針生さんに伺い、その時の近衛の眼差しを想像するに、当時の我が国の危機的状況と自責の念を重ねたのではないかと思うと、心中胸を揺さぶられる想いがします。

4.天の配剤
三代前からの私の家族史は将に「禍福は糾(あざな)える縄の如し」の譬えのとおりですが、それ以上に「天網恢恢、疎にして漏らさず」の本来の悪い意味ではなく、逆説として良い意味で、天のネットワークに見守られて自分や子供・孫達が生かされていると、今素直に思うことができます。
父が乗っていた列車を襲った米機パイロットの手元があと僅か数ミクロン違っていれば自分はこの世に生まれていないこと、父が困難な状況の中にあっても慶應義塾に入ることを志したことが私の進路をも左右したこと、岳父が将来そこに住むという確たる計画もなく購入した所沢の地所が家内との結婚を通じて私が耳庵に再会する機会を与えてくれたことなど、他にも単なる偶然とは考えられない出来事や関係性に包まれているからです。
壱岐と佐世保の違いはあるものの耳庵が私と同じ長崎県を故郷としていることや、耳庵との交流・協働の深かった「小林一三」が阪急や宝塚歌劇のみならず私が約40年勤務した会社(日軽金)の初代社長であったことにも偶然を超えるご縁を感じてしまいます。
振り返ると、大出前会長に誘っていただいて所沢三田会に入会後真っ先に参加した「歴史研究会」では、小野さんはじめ会員の皆さんから多くの知見や見識をいただき、ただ楽しむだけでなく現在生起している国内外の諸問題に真剣に向き合う気力と気概を戴いています。
「天網恢恢、疎にして漏らさず」という諺の本来の意味合いが「天は非道や悪事を赦さない」ということであれば、今世界に拡がりつつある専制覇権主義の政権に適用され、世界が天の配剤による平和を取り戻すことを切に願うばかりです。 (了)
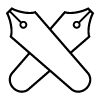
















コメント