上京から慶應卒業までが私の原点 佐藤和夫(S51文)
- 事務局
- 2021年1月15日
- 読了時間: 8分
更新日:2021年1月16日
<高校卒業後、杉並の新聞専売所に住み込む>

私は北海道釧路市の出身です。父は菓子職人で、北海道内を転々としていたため、きょうだい4人、道南から道東まで、みんな生まれた地域が違います。
私は中学生の頃から小説などを書く文学少年でした。家は貧しく、高校も日本育英会の奨学金頼みでしたが、高校2年生の頃、中央公論社が発行していた『高校文藝』という月刊誌に短編小説が入選、釧路の書店で平積みされていた雑誌を開いて、目次に自分の名前を発見した時の嬉しさは忘れることができません。
以来、本を読んだり、書き物をしたりにますます没頭。高2の時の受験模試でそれなりの成績だったことが逆に災いして、ほとんど勉強もせず文学青年気取り。駅近くの陸橋の真ん中あたりで真っ白な雪の中をくっきりと黒く遠く伸びていく何本もの鉄路を見ながら、「ここから抜け出したい」とぼんやりと考えていました。
そのうちに高校卒業の日が近づいてきました。担任の教師は「1年浪人すれば北海道大学には合格するはず」と言ってくれましたが、家にいても迷惑なだけ。
そんな折、住み込みで新聞配達をすれば家を出ることができると知り、親にも言わずに申し込んでしまいました。
3月も終わりの頃、道東はまだ雪と氷に閉ざされています。早朝の釧路駅を、ナップザックひとつを担いで出発しました。見送りに来た母親はホームで少し走って、あとは泣いていました。
急行列車で釧路―函館―青函連絡船―青森―上野と、27時間くらいの道程でした。こうして上京、東京都杉並区の毎日新聞今川専売所に新聞配達員として住み込みます。寒冷の地で育った人間にとって東京の暑さは堪えました。新聞休刊日も年に元旦の1日しかなく、労働環境は今では考えられないほど劣悪だったと思います。
<やはり大学に行かなければ>
住み込んで数カ月、午前3時に起床して朝刊を配達し、朝ご飯を食べて眠り、午後3時に夕刊を配ってまた眠ってしまう。何のための上京だったのか、よくわからない数カ月が過ぎました。
しかし落ち着いてくると、次第に周囲の状況が飲み込めるようになってきます。「俺には戸籍がないのだ」とうそぶく人、ほとんど人と話さない外国籍の人。
「俺はこれからどうなるのだろう」と考えていた矢先に相部屋になったのが、新聞配達をしながら大学を目指して受験勉強をしている3歳年長のMさんでした。
「そうか、それなら」と思い立って受験勉強を始めたのは9月過ぎの頃です。残すところ数カ月で後がありません。さすがに眠る時間を削って勉強したところ、慶應義塾大学と早稲田大学に合格することができました。
先に合格発表のあった慶應に行く、と即決。日吉なので、今度は日本経済新聞の新聞奨学生になり、入学金と授業料を借りて、横浜市白楽の日経新聞六角橋専売所に入りました。
慶應には、同じ高校の同期生のK君がいて、いろいろお世話になりました。K君は後に産経新聞の論説委員長になります。
<慶應と育英会からの奨学金を得て>
入学して1年後、日吉の掲示板を眺めていると、いろいろな「奨学生応募要項」のペーパーがいくつも掲示されていることに気がつきました。「あ、自分のような状況の学生は対象になるのではないか」と考えて応募してみると、返済不要の慶應からの奨学金に加えて、育英会の特別奨学金も支給されることになります。入学時に遡っての支給だったので、入学の際に新聞社から借りたお金は、きれいに清算することができたのでした。
奨学金があれば、月々の生活費も何とかなる。学費は休みにアルバイトをして貯めればいい。背中に翼が生えたような気持で、川崎駅の近くの3畳一間のぼろアパートで独り暮らしを始めます。
<学生劇団の立ち上げ>
新聞販売店を辞めて最初にやったことは、なけなしのお金で「劇団員募集」のチラシをつくり、「幻の門」の前で登校する学生たちに配布して学生劇団「羅睺羅(ラゴラ)」をつくったことです。芝居などろくにやったことがないのに無茶苦茶な話ですが、それでも20数名の劇団員が集まり、教本を片手に見様見真似で訓練、公演を打ったりしていました。
今から5、6年前に慶應の50歳代の準教授にお会いした際、「ラゴラという劇団、学生時代にありましたよ」と仰ってくれたので、少なくとも十数年は存続したのでしょう。
ところが学業と、芝居と、アルバイトの鼎立はさすがにきつく、破綻してしまいます。「早朝の仕事であれば芝居の稽古ができる」と考えて、朝7時から9時半まで、浜松町の世界貿易センタービル39階~42階までのビル掃除のアルバイトをしていたのですが、その結果、一時限のフランス語講義が単位不足になって留年、すべての奨学金が支給停止となったのです。
泣く泣く劇団の団長を辞め、学費と生活費稼ぎに奔走する羽目となりました。飯場での住み込みから晴海の荷揚げ作業までたいていのことをやりつつ、国文科の池田弥三郎先生のゼミに入り、何とか5年で卒業することができたのでした。
<辛うじて就職>
卒業当時は第一次オイルショックと第二次オイルショックの間の時期で景気は最悪。あの頃は「学部指定制度」なるものがあって、文学部出身者は教師か公務員、マスコミ関連くらいしか応募先はなかったように思います。
「演劇関係に進めれば…」とも思いましたが、親に仕送りをしなければ、と考えて卒業間際からずいぶん出遅れの就職活動を始めました。アルバイトができないので困窮しましたが、先に卒業した友人からお金を借りるなどして凌いだ記憶があります。
時期外れなので、新聞の「人材募集」記事欄くらいしかあてはありませんでしたが、何社かの出版社を受けているうちに何社かに合格、給料が比較的高かった中経出版(現KADOKAWA)に入社して雑誌編集部に配属となりました。その4年後に、「君がやれ」と指名されて編集長になります。
あの頃は、雑誌編集者の休みと言えば月に1日程度。今で言う「働き方改革」など夢のまた夢、という時代でした。

<あさ出版の立ち上げ>
よく働き、よく飲んだ前職時代でしたが(その後もあまり変わりませんが)、30代も半ばを超えると、またぞろ虫が騒ぎます。「ずっとこのままでいいのか?」「おまえは、バスのお客さんのままでいいのか?」。
「やっぱり、自分で自分の人生のハンドルを握りたい」「ガス欠になっても、道を間違えても、自分の運転ならば後悔はない」――そんなふうに考えて独立、1人で東京都文京区のアパートを借りて株式会社あさ出版を設立しました。コンセプトはたったひとつ。「今がどんなに暗くても、必ず朝はやってくる」。みんながそう思えるような本をつくりたい、というものでした。

一人起業でしたが、30年を経過するうちに社員数年間の新刊出版点数も70~90点前後となりました。いろいろな書籍を出版してきたので、今では特に強い分野というものはありませんが、『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズ(坂本光司氏著)や、『新幹線 お掃除の天使たち』(遠藤功氏著)などは、自分自身がつくった書籍として印象深いものがあります。

と、昔のことばかり書きましたが、これも、新聞販売店で働くために上京してから慶應を卒業するまでの6年間が、幼児期から少年期にかけてとは別の、もう一つの私の原点のように感じるからです。
他大学に進学していれば、私はおそらく中退していたでしょう。食うや食わずの時は、友人の家でお母さんの手料理をたらふくご馳走になりました。劇団では一生ものの友人ができ、彼らが、起業の際にも力を貸してくれました。こうした意味からも、慶應という大学に感謝しています。ずいぶん以前から出版三田会にも顔を出しており、そこでも多くの知己を得ることができました。
所沢三田会には、飲み仲間、というより大先輩の山田弘雄さんのご紹介で入会しました。現在は、この11月に社長職を譲り、代表取締役会長となったばかりでまだまるきり現役ですが、しばらく後にはフリーな時間が増えるはずです。その際にはもっと顔を出させていただきます。その節は、よろしくお願いいたします。
(感想)
今回会員紹介欄に投稿頂いたのは釧路の高校卒業後、即故郷脱出新聞配達を起点にドラマチックな人生を送られてきた佐藤和夫さん(S51文)です。
今は、自分で立ち上げてこられた「株式会社あさ出版」の代表取締役として又、「人を大切にする経営学会」の常任理事等現役で活躍されています。
最初に頂いた原稿を読ませて頂いた時に、色々ご苦労されてこられた内容でしたのでさぞかし厳しい人生哲学的な雰囲気をお持ちの方かと思いましたが、お会いし話を伺い坦々と昔を振り返る語り口は大変印象に残りました。
しかし、まだまだ寄らば大樹的な考え方が支配的な時代この開拓者スピリッツはどこから溢れてきたのでしょうか大変興味ありますね。
ご本人にも直接お伺いしましたが、いつのターニングポイントでも先を見て悲観的になる事はあまりなかったそうです。
自分を表現すること又自分の世界を持つことに小さい時からこだわりがあり、そのこだわりのままに生きてきたように感じるとのことです。
今回頂いた原稿は人生の原点ということですが、まだまだ人生の書き尽くせないストリーがありそうです。
これからの折々にその続編の披瀝をお願いできればと思います。
会長職の退職も近い将来見据えられているそうで、その時は是非当会に積極的に参加して頂いての新たな風を期待しています。
記 松尾 基昭(S47経)
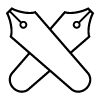
















コメント