歴史研究会5月例会 国分寺周辺視察報告
- 事務局
- 2025年5月9日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年5月11日
素晴らしい青空に晴れ渡った連休明けの新緑に風薫る皐月の5月7日(水)10時前、秋津駅に10名が集合し、新秋津から西国分寺駅まで武蔵野線にて移動しました。西国分寺周辺は当初のイメージとは異なり、都営系のマンション群が立ち並ぶ中を散策しながら、立派な東京都公文書館や国分寺市役所を横目に歩いて行く途中の右手に大きな森があり、その中に神社がありました。そして、その奥に佇む大きな屋根を見つけ、あれは何だろうと見に行ったら、それこそが最初の目的地である武蔵国分寺という名刹の薬師堂でした。その横道は南側に面した表参道ではなく、北参道だったようです。
武蔵国分寺は真言宗豊山派(本山:奈良の長谷寺)の寺院で、ご本尊は薬師如来、山号は医王山、院号は最勝院です。奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、武蔵国国分寺の後継寺院にあたります。
武蔵国の国分寺は、元弘3年(1333年)の「分倍河原の戦い」で焼失しました。足利尊氏に呼応して討幕軍を起こした新田義貞の20万7千兵まで膨れ上がった軍勢は鎌倉街道沿いに南下し、入間川を渡り、迎撃に来た桜田貞国率いる3万の鎌倉幕府軍を5月11日に「小手指原の戦い」で、5月12日に「久米川の戦い」で相次いでず撃破しました。幕府軍は、武蔵国の最後の要害である多摩川で新田軍を食い止めるべく、分倍河原まで撤退して食い止めようと軍勢を立てなおしにかかりました。しかし、新田軍は2万の兵力で分倍河原に一気に押し寄せ大勝利し、北条泰家以下は壊滅して敗走し、鎌倉幕府崩壊へと繋がります。この「分倍河原の戦い」において、ご本尊の釈迦如来像は焼失しましたが、薬師如来は担ぎ出され助かりました。
そこで責任を感じた新田義貞は建武2年(1335年)に旧国分寺の金堂跡に助け出された薬師如来を祀る薬師堂を建て、後継となる武蔵国分寺のご本尊として崇められ今日に至っております。現在の建物は江戸時代の宝暦年間(1751年~1763年)に再建されました。その薬師如来坐像は平安時代の作とされ、木彫寄木造で像高が約1.95m、膝開きは約1.4mにもなり、表面には金箔が施されていたそうですが、現在は金箔の多くが剥がれ黒漆の部分を呈しているそうです。でも秘仏として一般公開されていないので、ご尊顔を拝することはかないませんでした。毎年10月10日(目の日)の御開帳法要にて、年一回の一般公開で拝むことができます。作者は不明ですが国の重要文化財です。

仁王門は入母屋造の八脚門で、宝暦年間(1751年~1763年)の建立です。立派な「阿形」と「吽形」の仁王様が寺域を守っています。また、楼門は徳川譜代の米津氏菩提寺である東久留米市の米津寺が明治28年に焼失した時、唯一残った楼門を武蔵国分寺に移築したものです。これら薬師堂・仁王門・楼門は、国分寺市の重要文化財に指定されております。
非公開となっています本堂には阿弥陀如来がまつられているそうです。御朱印をいただこうとしたのですが、現在はやっていないとの貼り紙があり、残念でした。また、境内には自由に入れる「万葉植物園」というのがあります。元国分寺住職が昭和25年~38年(1950年~1963年)の間に万葉集に歌われた植物160種を集めて造った植物園で、万葉集に出てくる歌の碑が掲げてあります。しかし雑草も多く、歌に歌われた植物の特定が難しく、正直よく分かりませんでした。もう少し見る人に寄り添っていただければと思いました。拝観料が無いのでやむを得ないのかもしれません。この植物園も市の天然記念物に指定されています。その奥の方に、武蔵国国分寺時代に存在した七重の塔のミニチュア版がありました。
その後、公園になっている武蔵国国分寺跡を通りました。講堂や金堂と須弥壇、そして七重の塔の跡地として敷石や石塀が現存しています。聖武天皇の時代、天武天皇の孫の長屋王と藤原不比等の息子である藤原四兄弟が壮絶な権力争いを行い、その結果、長屋王は敗北し一族は滅亡しました。絶対権力を握った藤原四兄弟は聖武天皇さえ圧倒する勢いでした。ところが遣唐使がもたらした天然痘が猛威を振るうようになり、当時の総人口の3割が死亡するという大惨事となり、農民人口が激減し、国全体が飢饉状態に陥りました。挙句、絶頂を誇った藤原四兄弟が相次いで全員死亡し、藤原氏の権勢が衰えました。当時、朝廷でご意見番を担っていた陰陽師が、「これは長屋王の祟りだ」と断定し、人々は平城京を「祟りの都」と恐れおののきました。
聖武天皇は最先端の仏教に頼り、祟り鎮魂を国家プロジェクトと定め、最初に巨大な廬舎那仏(奈良の大仏として現存)を建立し、国ごとに国分寺と国分尼寺を建立しました。国分寺には七重の塔も建立しました。国分寺という地名が現存しているのは全国でも珍しい事だと思います。
武蔵国国分寺跡を通りながら食事処「デニーズ」へ行きました。歩き回った後のビールは格別でした。
食後、武蔵国分寺の境内前を流れている「真姿の池湧水群」に沿った「お鷹の道」を散策しました。江戸時代、この地域は尾張徳川家の御鷹場でしたので、それにちなんで清流沿いの小道を遊歩道として整備して「お鷹の道」と名付けたそうです。
「真姿の池」をはじめとする崖線下の「湧水群」は、昭和60年(1985年)に環境省選定名水百選のひとつに選ばれ、東京の名湧水57選にも入っています。「真姿の池」とは、嘉祥元年(848年)の頃、不治の病に苦しんだ玉造小町が病気に苦しみ病気平癒のために国分寺を訪れて21日間薬師如来を参拝しました。すると一人の童子が現れ、小町を池のほとりに案内し、この池の水で洗い清めるようにと言ってすぐに姿を消しました。小町が身を清めると、いつの日か病は癒え、元の姿、つまり「真姿」に戻ったそうです。この言い伝えによって、「真姿の池」と呼ばれるようになったそうです。そして、今は弁財天が祀られています。
ここで、武蔵国分寺跡資料館へ行く組と、そのまま国分寺駅から帰宅する組に分かれる事になり、解散となりました。筆者は資料館組に加わりましたが、誠に残念ながら資料館は休館でした。やむなく武蔵国分寺の西側にある八幡宮をお詣りし、国分寺市役所一階ロビーに鎮座するミニチュア模型の国分寺七重の塔を見学しました。
そして隣接する東京都公文書館の展示コーナーを見学しました。参考になったのは川越鉄道でした。現在の中央線御茶ノ水から八王子まで運行する私鉄甲武鉄道の子会社である川越鉄道が1894年に敷設した路線が国分寺駅から川越駅まででした。1920年に武蔵水電に合併後、1922年に鉄軌道事業が分離されて(旧)西武鉄道の路線となりました。1927年に東村山駅から高田馬場駅間が開業すると国分寺駅から東村山駅間は分離され支線となり、西武国分寺線となりました。そして、川越から東村山までの路線がそのまま高田馬場まで繋がれ、現在の西武新宿線になっています。1945年に(旧)西武鉄道は本路線開業後に創業した武蔵野鉄道に合併され、西武農業鉄道の路線となり、1946年に西武鉄道に社名変更して今日に至っております。
ところで、武蔵国分寺の門前一等地に本多一族のお墓群が並んでいるのが気になり、八幡宮の寄付寄進覧にも本多一族が並んでいるので、この辺は本多一族の勢力なのかなと思っていたら市庁舎で三代目市長の名が本多というのが判明しました。調べたら、この周辺の有力な名主で本宅は「お鷹の道」にあり、一般公開されておりましたが、残念ながら知らなかったために素通りしてしまいました。案内板も無かったように思いますので、気づきませんでした。
公文書館を後にして西国分寺駅まで行き、解散しました。国分寺という地域は文化財が豊富でいくらでも観光誘致が可能な魅力的な施設や文化を持っているにもかかわらず、ルート案内もあまり無く、ほとんど何もしていない事を残念に思い、もったいないなと感じながら帰途につきました。
文責:伊藤芳康(S51経)
写真:南 博幸(S51法)
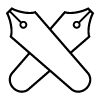


































コメント